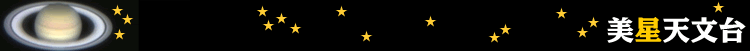
|
|
|
矮新星と確認 |
|
|
米アリゾナ州のカタリナ山脈のビゲロー山に設置された口径68cmのシュミット望遠鏡を使って、地球に近づく危険な小惑星(地球近傍小惑星)を探索するプロジェクト「カタリナ・スカイ・サーベイ」で撮影された画像から、アリゾナ大学月惑星研究所のE.J. クリステンセン氏が、明るくなっている天体を発見しました。 この増光天体の位置には、以前は約21等級の星がありましたが、2006年10月28日と11月17日のカタリナ・スカイ・サーベイで得られた画像には、それぞれ13.9等級と14.4等級の星として写っていました。つまり、この天体は約7等級(明るさにして500倍)も明るくなったことになります。 2006年11月20日の国際天文学連合中央局メールニュースに、この増光現象が報じられました。新星爆発かもしれないため、美星天文台では、11月22日未明に101cm望遠鏡を使って分光観測をおこないました。その結果、古典的な新星爆発ではなく、矮新星(わいしんせい)の「アウトバースト」と呼ばれる現象であることが分かりました。 |
|
 矮新星の概略図 |
矮新星とは、恒星のなれの果てである白色矮星と低温度星が連星となっている系で、低温度星から表面のガスが白色矮星に流れ込んで、白色矮星の周りに円盤を形成しています。この円盤のことを降着円盤と呼んでいます。 矮新星のアウトバーストとは、降着円盤に降り積もるガスの量がある限界に達し白色矮星に一気に落ち込む時に円盤の温度が上昇して、明るく輝きだす現象です。 |
同じような増光現象としては、愛知県豊橋市の新天体捜索家・長谷田勝美(はせだかつみ)さんが、2005年3月16日に発見した増光天体も矮新星のアウトバーストでした。 |
|
図中左が美星天文台で分光観測をする際に撮影した画像で、黄色い矢印で示している天体が、増光天体です。この天体は右の1990年に撮影された同じ場所の画像には写っていないほど暗い天体でした。 |
|
上のグラフが増光天体のスペクトルです。左上がりのスペクトルは、数万度の高温の物体から放射されていることを示しています。また、水素による吸収線(Hα、Hβ、Hγ、Hδ)が目立ちます。よく見ると水素のHα線とHβ線の中心に輝線があることが分かります。こうしたスペクトルの特徴は、古典的な新星爆発ではなく、矮新星のアウトバーストによるものです。 |
|
|
【参考】 CBET 746 VARIABLE STAR IN LEO, E. J. Christensen CBET 753 VARIABLE STAR IN LEO, K.Ayani, T. Kato |
|
[2006.11.26 掲載] |
|
Copyright(C) Bisei Astronomical Observatory All Rights Reserved.

