美星天文台は、超新星探し共同プロジェクト(SNOWプロジェクト)に参加しています。
超新星は、星が大爆発を起こし、太陽の100億倍もの明るさで輝くものです。一つの銀河ではだいたい100年に1個の割合で、星が超新星爆発を起こすと言われていますが、まだ十分な統計データがありません。
そこで、国内の7つの公開天文台と2つの大学が協力して、超新星探しプロジェクトを始めています。
宇宙には、多数の銀河が群をなしているところがあり、銀河団と呼ばれています。これを撮影すると、一つの写真(CCD画像)に10個以上の銀河が写ります。7つの公開天文台で分担してたくさんの銀河団を撮影すれば、超新星を発見する確率が高くなりますし、また、超新星爆発が起こる確率もわかるでしょう。
![[13KB JPEG]](snow_img/a2626s.jpg) |
左の写真は、8月27日に美星天文台の101cm望遠鏡とCCDカメラで、ペガススの四辺形の真ん中近くを撮影したものです。真ん中近くの2つの大きな銀河は、IC5337(右)とIC5338(左)です。
まわりの小さく写っている天体のうち、輪郭のはっきりしたものは我々の銀河系の星ですが、(わかりにくいですが)輪郭がぼやけたり、形がひしゃげたりしているものは遠くの銀河です。ここにはエイベル2626という銀河団が写っているのですが、群をなしている一つ一つの銀河は遠くて小さく見えるため、この小さい写真では星との区別はつきにくいですね。
では下の写真をご覧ください。 |
![[JPEG 7KB]](snow_img/a2626p.jpg) |
左の写真は、上の写真の上端真ん中あたりの部分を取りだしたものです。真ん中よりやや右の天体と、真ん中より左上の明るい天体は輪郭がはっきりしているので、私たちの銀河系のなかの星だと判定できます。その他の天体のうち、最も上の天体と最も右の天体は前の2つほど明確ではありませんが、これも星でしょう。
その他はすべて輪郭がかなりぼやけているので、遠くの銀河と考えてまず間違いありません。(なお、星の形が丸くないのは、望遠鏡のガイドの誤差によるものです。改善努力中!)。非常に小さい白い点のようなものは、宇宙線などによるノイズです。 |
これを別の日に撮影した写真と見比べて、明るくなっている銀河が見つかれば、そこに超新星が爆発したとわかるわけです。
私たちのプロジェクトで監視している銀河団は、ほとんど楕円銀河の集まりです。
楕円銀河で見つかる超新星は、Ia(いちえい)型に分類される種類のものです。Ia型超新星は、赤色巨星に進化しつつある星とペアを作っている白色わい星に、相棒の星のガスが降り積もり過ぎてついには木っ端みじんに爆発してしまったものです。Ia型超新星は最大光度がどれでもほぼ同じになると考えられるため、これを利用して遠くの銀河の距離を測ることができます。(詳しい解説は準備中)
|
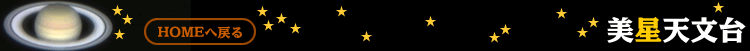
![[13KB JPEG]](snow_img/a2626s.jpg)
![[JPEG 7KB]](snow_img/a2626p.jpg)