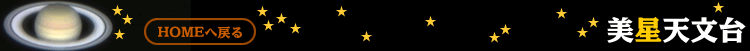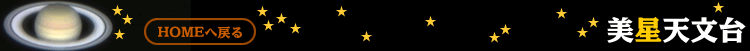|
| ポインティング
|
| 101cm望遠鏡では、ポインティング(天体の導入)は計算機が自動で行います。 |
|
| 1.望遠鏡解析(Telescope
Analysis) |
101cm望遠鏡は、計算機に天体の座標を与えることによって自動で目的の天体を導入できます。
しかし、実際には
● エンコーダーの原点のずれ
● 望遠鏡の極軸のずれ
● 望遠鏡の赤経軸と赤緯軸の非直交性
● 望遠鏡の赤緯軸と望遠鏡軸との非直交性
● フォークのたわみ
など機械的な誤差によって、完全に目的の天体の方向には向きません。
望遠鏡解析とは、このような望遠鏡の機械誤差を解析することです。
望遠鏡解析には、TPOINT を使用しました。
(TPOINT は、Starlink Project の P.T.Wallace氏 作です) |
|
| 2.
天体導入の高精度化 |
101cm望遠鏡では、望遠鏡解析を行った後、その結果を望遠鏡制御ソフト(Telcont.exe)での座標計算に反映させることで、高い精度で天体を導入する事ができます。
補正をする前は、導入精度が35.1秒角であったものが補正を行った後は6.3秒角になりました。
▼下の図は、天体を自動導入した時、望遠鏡の視野のどこに星が現れたかを示す図です。
様々な方位と高度の星を使って測定しました。
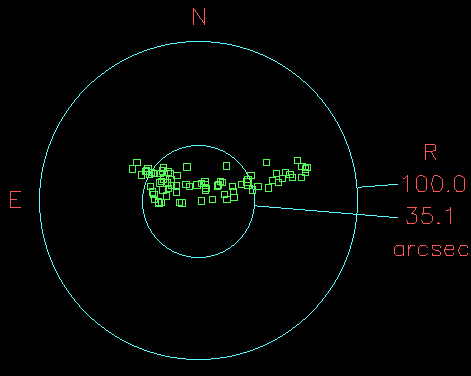 |
| 機械誤差の補正をする前、導入精度
35.1 秒角 (97.5.9) |
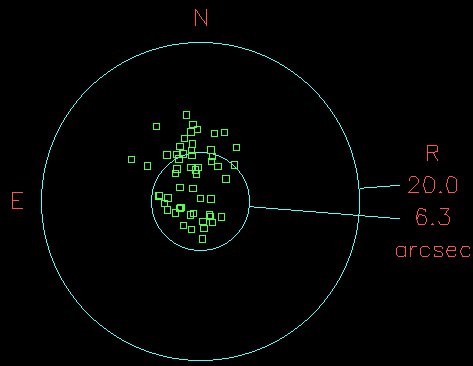 |
| 機械誤差の補正をした後の導入精度
6.3 秒角 (97.5.9) |
|
|
|