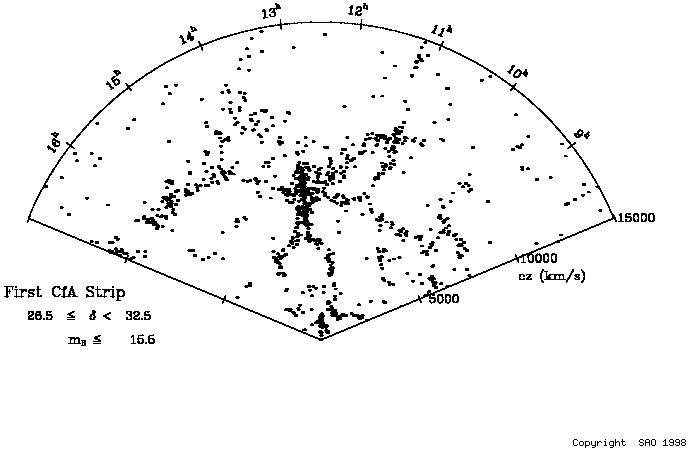
|
|
|
宇宙にひろがる銀河の空間分布を数億光年以上のスケールで眺めると,泡のような構造がみられる.銀河は泡の膜にあたる部分に分布している.細胞状構造,ボイド・フィラメント構造とも呼ばれる. 1980年代から近傍の多数の銀河の赤方偏移の観測が行われ,ハッブルの法則により赤方偏移が銀河の距離に比例するものと仮定して,宇宙空間の奥行き方向の銀河分布が求められるようになった.その結果,銀河の分布が3次元的に求められ,銀河が泡状に分布していることが発見された.泡の膜にあたる部分には銀河群・銀河団が連なっていて超銀河団を形成し,その一方,泡の空間にあたる部分には銀河がほとんど存在しない空洞(ボイド)が広がっている.空洞の大きさは1億光年以上に及ぶ.従って,数億光年以下のスケールでは宇宙の一様等方の仮定(宇宙原理)は成り立たない. この泡構造を理論的に再現することが現代宇宙論の課題のひとつとなっている. |
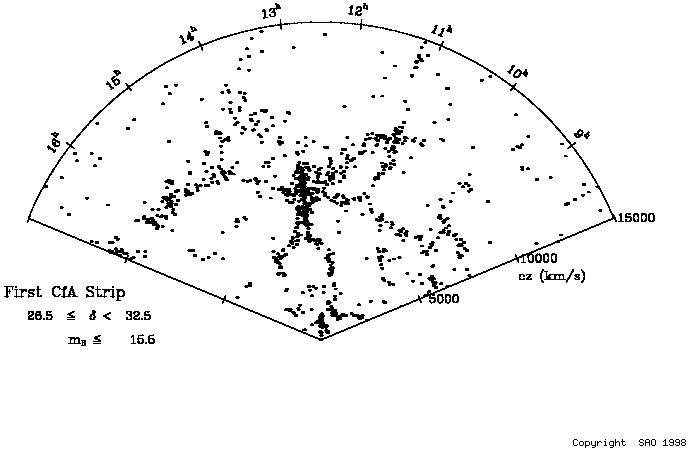
|